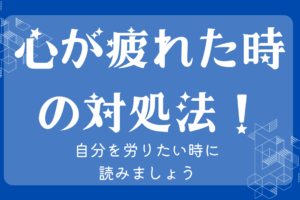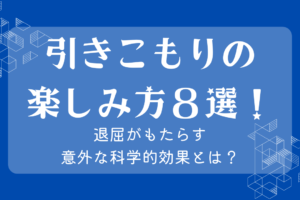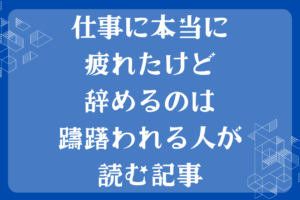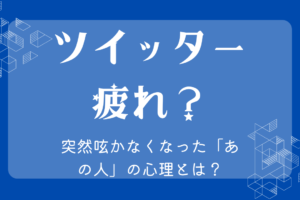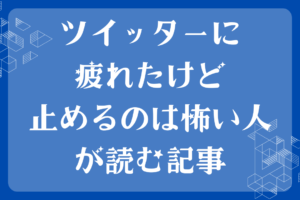日本に昔から伝わる妖怪の一つに「七歩蛇(しちほだ)」という妖怪がいる。七歩蛇に噛まれると七歩歩くうちに死んでしまうので、この名前がついたそうだ。七歩蛇は体長12センチ、真っ赤な身体に4本の足が生えている。
さて、先日川上弘美先生の『蛇を踏む』を読んだ。以前から川上弘美先生のファンである私は、それぞれの本を一度だけでなく二度三度読んでいる。
そんな私だがどうした訳か『蛇を踏む』だけは遠い昔に一度読んだきりで一切再読しておらず、内容もうろ覚えになっていたのだ。
何かと話題になる「蛇の正体」についても私なりに考察してみた。今回は『蛇を踏む』の読後にふつふつと湧いた思いを書き連ねてみたい。
川上弘美『蛇を踏む』あらすじ
主人公の「サナダさん」は数珠屋「カナカナ堂」の店番として働いている。そんなサナダさんはある日ミドリ公園に行く途中の藪で蛇を踏んでしまった。その蛇はどろりと溶けて形を失ったあと、50歳くらいの女性の形になって、いつの間にかサナダさんの家に住み着く。
カナカナ堂のオーナーであるコスガさんと数珠職人である奥さんのニシ子さんと静かに過ごすサナダさんの日常。実はコスガさんとニシ子さんのところにも蛇がいるらしい。人々の静かな日常に蛇はじわじわと絡み込んできて…。
川上弘美『蛇を踏む』の「蛇」は何を表している?
『蛇を踏む』では蛇が擬人化して描かれ、昆布と細切りニンジンの和え物を作ったりビールを冷やしたりしている。サナダさんのところの蛇は自分を「サナダさんの母」だと名乗り、コスガさんのところの蛇は自分を「ニシ子さんの叔母」と名乗る。蛇はサナダさんたちの日常に淡々と馴染みながら「ヒワ子(サナダさんのこと)ちゃんも蛇の世界に入らない?」と誘うのだ。
では『蛇を踏む』の「蛇」は何を表しているのか。あくまでも個人的な感想だが、私は2つの意味があるのではないかと考えた。それは「社会の枠組み」と「相手との心理的な距離」だ。
社会の枠組みというのは、人があるべき姿として求められる枠組みのことで、それは時代によって揺ら揺らと変わる。「家庭を持って良い仕事をして、みなのお手本になるような人生を歩む」というある種スタンダードな枠組みは、蛇のように人の心に絡みつく。その枠組みに入ってしまえば(蛇の世界に入ってしまえば)ある種「楽」ではある。しかしその枠組みは時に人をきつく締め付け、がんじがらめにし、苦しめるのだ。
主人公のサナダさんは、若い女性である。(作中で年齢は明かされていないが、2人の弟が大学生と高校生であるので、20代だと推察される)そんなサナダさんは元教師だが4年で辞めカナカナ堂という数珠屋で働いている。また、カナカナ堂の主人であるサナダさんは、夫のいたニシ子さんと駆け落ちをしてコソコソ逃げるように数珠屋を営んでいる。カナカナ堂で働く3人には、どこか「蛇の世界に入れない」=「社会の枠組みからはみ出ている」感じがあるのだ。
また、サナダさんのところの蛇がサナダさんにいつも言っている言葉がある。それは「ヒワ子ちゃんはいつまでたっても知らないふりばかり」というセリフ。サナダさんを語り手とした、こんな記述もある。
「人と肌を合わせるときのことである。その人たちと肌を合わせる最初のとき、私はいつも目をつぶれない。その人たちの手が私を絡め私の手がその人たちを巻き、二人して人間のかたちでないような心持ちになろうといつときも、私は人間のかたちをやめられない。いつまでも人間の輪郭を保ったまま、及ぼうとしても及べない。目を閉じればその人に溶け込んでその人たちと私の輪郭は混じりあえるはずなのに、どうしても目をつぶれないのである。」
(『蛇を踏む』44ページより引用)
作中、サナダさんの蛇が身体に入り込む場面がある。外耳道から蛇が入り込み、液体となり奥に流れ、阻止しようと頭を左右に振ると、ぬるぬるとした水に変わった蛇が内耳へと向かう。ねばねばとした蛇の水が三半規管を満たし、神経を撫で、脳が蛇で満たされる…。想像しただけで、ゾッとするようなシーンだが、それでもサナダさんは蛇にはならない。さわらの西京漬けなどを淡々と口にし、蛇になどなるまいと念じる。
じわじわと迫りくる蛇と、淡々と生きる登場人物たちのコントラストが、作品のシュールさを引き立てているようだ。作品は、サナダさんが蛇に首を絞められながら蛇の世界に来るよう迫られるシーンで終わる。サナダさんもまた蛇の女の首を絞めながら「蛇の世界なんてないのよ」というラストシーン。社会の枠組みなど本当は存在しない。人と混じり合うことなど本当はできない。私にはそのようなメッセージが感じられた。
川上弘美『蛇を踏む』は感覚的に残る作品
ちなみに作中で、カナカナ堂のニシ子さんのところの蛇は死ぬ。ニシ子さんは蛇についてこんなふうに語るのだ。
「ねえ。サナダさんの蛇はどんな蛇なの。あたしの蛇はね、もうすぐ死ぬわ。あたしは悲しくてしょうがない。こんなに愛しているのに。あたしはね、蛇になりたかった。どうしてあのとき蛇の世界に行かなかったのかしら。誘われたのよ。サナダさんも誘われるでしょう。蛇は何回でも誘うわ。」
(『蛇を踏む』42ページより引用)
蛇の正体は同じではない。そして、ニシ子さんのように蛇を愛しながらも蛇の世界に行かなかった者、サナダさんのように蛇の世界になんか行くもんかと念じている者、蛇に対する距離の取り方も人それぞれなのだ。
川上弘美先生の言葉には魂が宿っているようで、選ばれた言葉の後ろに連なるいくつもの言葉が見えるようである。選んだ言葉だけでなく、選ばなかった言葉で形を作って作品の深みを作り出す、川上弘美先生の作品にはそんな魅力があると思う。
蛇の正体については深読みしてしまったが、川上弘美先生が「深い意味はなく湧き上がる水滴をすくい取って紡いだだけなんですよ」なんて仰るのなら、それはそれで深い気がする。