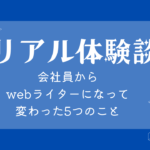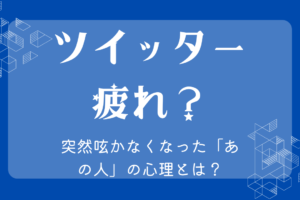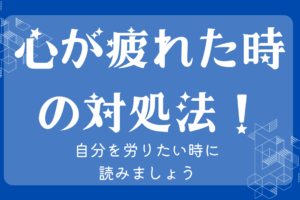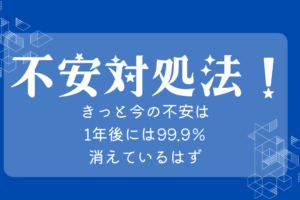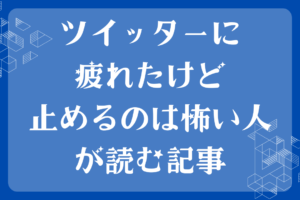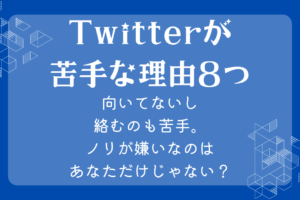「OK」という言葉の由来は“all correct”なのだという。なぜ“all correct”がOKになるのかと言うと、アメリカの第八代大統領マーティン・ヴァン・ビューレン氏の愛称“old kinderhook”の頭文字にならい“all correct”を“oll korrect”と表記するようになったのが始まりだそうだ。“oll korrect”なんて嘘みたいな偽りの表記だが、今やOKという言葉は英語圏だけでなく世界中で通じる一般的な言葉となっている。
「嘘」はいつから「真実」に変わるのか。嘘と真実の境目はどこにあるのか。そんな深遠な問いを投げかけてくれるのが、文豪安部公房先生による『人間そっくり』だ。今回は、何度も何度も嘘と真実が、正気と狂気がひっくり返される『人間そっくり』の感想を書いていきたい。
安部公房『人間そっくり』のあらすじ
主人公の男は『こんにちは火星人』というラジオ番組の脚本を担当している脚本家だ。火星人の存在をほのめかし人々に夢を与えていた男だが、火星ロケットが打ち上げられたことでリスナーから「嘘をついていたのか」とクレームが続出し、番組は終了に追い込まれてしまう。
そんな時男の家に「火星人」を名乗る男がやってきた。男は自分を火星人だと言うが「自分を火星人だと信じている気の狂った地球人」なのか「自分を火星人だと気づかれたくなくて気狂いの地球人のふりをしている本物の火星人」なのか、その存在の境界線はゆらゆらと揺らいでいく。
「自称火星人を名乗る男」の妻は、男を気の狂った地球人だと言うが、男は妻を「気の狂った火星人」だと言う。果たして真実はどこにあるのか?そもそも真実など存在するのか?トポロジーの世界に主人公の男はどんどん引きずり込まれていく…
「真実」を「トポロジー理論」が破壊ーー安部公房『人間そっくり』
「その奇妙な男は、ある晴れた五月の昼さがり、ミシンのセールスマンなんぞのような、のどかな足取であらわれた。」
(『人間そっくり』5ページ目より引用)
安部公房先生の『人間そっくり』はこんな冒頭文から始まる。自称火星人の男は、ただの気狂いかと思いきや、自分を気違いだと思わせ、強烈な印象を与えることでビジネスを成功させようとする敏腕サラリーマンかと思いきや、火星から派遣された地球人そっくりの火星人…かも知れないのである。
本書のほとんどは、脚本家の男と「自称火星人」の男との会話で構成されている。
「ねえ、先生…念のためにもう一度うかがっておきますが、先生は、ぼくが火星人だってこと、本気で信じて下さったんでしょうね」
「くどいな、君は。信じたからこそ、こうしてすすんで、あんなテストを受けもしたんじゃないか。それをいまさら、無意味だなんて…無責任にも、ほどがあるよ!」
(『人間そっくり』74ページより引用)
『人間そっくり』のテーマは「トポロジー」である。トポロジーとは
トポロジーは、何らかの形(かたち。あるいは「空間」)を連続変形(伸ばしたり曲げたりすることはするが切ったり貼ったりはしないこと)しても保たれる性質(位相的性質または位相不変量)に焦点を当てたものである。
(Wikipediaより)
とのことだが、本書では地球人と火星人、ひいては自分と他者の線引きの曖昧さを強調するための道具として用いられている。
地球人と火星人は似ていない。似ていないからこそ区別ができる。区別ができるから安心感がある。これは地球人どうしが同じカテゴリーに属すと認識することで安心感が得られるのと同じだ。では、地球人と火星人が「そっくり」だったらどうか。
「区別のつかない未知の他人がいるらしいという、そのことだけで、人はすべての他人が信じられなくなり、互いに摘発し合い、密告し合い、中傷しあって、ついには国全体が秘密警察の巣みたいになってしまう」
(『人間そっくり』144ページより引用)
ネタバレになってしまうが、本書では結局男が地球人なのか火星人なのか答えは分からない。分からないことの不気味さが本を持つ手から身体中にじわりと染み込むような終わり方なのだ。
自分は地球人だろうか?
地球人だと信じて疑わなかったが実は火星人ではないのか?
自分が地球人だという「公理」は証明できないから公理なのだ。信じて疑わなかった公理に、ドロドロとした異物が溶け込んでくる。確固とした真実が揺るがされる。水分を吸い込む根のように異物が真実を崩していく。
隣に座る人が地球人だとどうしたら証明できるだろう。「火星人などいないから」などというつまらない「常識」を重ねれば重ねるほど真実はトポロジーのようにぐにゃりと形を変えて、真実の隙間を通り抜けていくのだろう。
安部公房『人間そっくり』を読んで
「自称火星人」の男の言動にとにかく振り回された。結局、火星人?地球人?と答えを急いでいると、とにかくイライラする。本文のほとんどが、2人の男が話しているだけなのに、人間の存在という究極のテーマを訴え続けているのがすごい。私もまんまと「自称火星人」の男の弁舌に翻弄されたが、非常に楽しい読書体験だった。